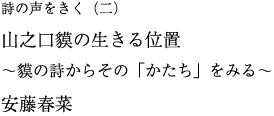

photo by ©Kozo Kaneda
目次
はじめに
山之口貘の道
1-1.貘の生涯
1-2.詩の特色
1-3.詩への評価
貘の位置
2-1.貘の「尖り」
2-2.「柄」を着る行為
詩と貘
3-1.「喰う」行為
3-2.「詩」と「生」
時代と貘
4-1.時代性
4-2.貘のもつ「ユーモア」
4-3.批評精神
5.おわりに
参考文献
はじめに
わたしが中学生のとき、高校生だった姉に届いたはがきにはこう書いてあった。「物質的なものよりも、目に見えないものを意識してみて。幸せに成りましょう。」その言葉を見た瞬間、なんだか簡潔で、素敵なことを言っていると思った。よく分からないけれど、憧れる世界の言葉だった。とても純粋だったわたしは、それから「目に見えない」ものを探すようになった。それがどのようなものなのか、わけもわからず、そんな「かっこいい」世界に、かぶれてみたかったのだ。少しはひねくれた現在でも、わたしは、その「かっこいい」世界を完全に蹴り倒すことができずに、そこになにかしらの命綱を繋げたまま生きているような気がする。「目に見えない」ものが、一体、どんなものなのかも見ようとせず、そこに逃げ道をつくるわたしには、なにがみえているのだろうか。「見えないもの」の可能性を認めながらも、そこに憧れを投影するのは、もうやめたい、とおもった。「見えないもの」のかたちを、みるべきなのではないのかと、おもったのだ。
いまからおよそ100年ほどまえ、山之口貘という詩人が生まれた。この詩人は、世の中が戦争の混乱によって緊張感を持ちはじめた1930年代の東京に生きながら、ろくな反戦詩も書かず、人間の混乱のうえをひょいひょいと飛び越えながら、そんな「僕」のことを詩に書いていた。彼は「人並み」に恋をし、「人並み」に結婚し、「人並み」以上の貧乏に苦しみ、ほとんど1冊の詩集を残したまま、あっけなく死んでしまった。掴みどころのない、間の抜けたような人生を送った彼の書く詩もまた、意思があるようでないような、指の間をするするとすり抜ける、かたちにならないものがある。
鮪の刺身を食いたくなったと/人間みたいなことを女房が言った/言われてみるとついぼくも人間めいて/鮪の刺身を夢みかけるのだが/死んでもよければ勝手に食えと/ぼくは腹だちまぎれに言ったのだ
「鮪に鰯」1
この詩をはじめて知ったのは、中学生のころ『山之口貘をうたう』というアルバムを聞いた時だった2。そのアルバムには、さまざまな貘の詩がうたわれていたが、この「鮪に鰯」の歌詞にわたしはくぎ付けになってしまった。なぜ、この夫婦は鮪が食べられないのか。詞の奇妙さに惹かれながらも、その意味をなかなか理解できなかったわたしと姉は、しだいにその詩に自分たちの物語をつくりはじめ、鮪を食べられないのは、この夫婦が猫であるからだ、ということで、「鮪に鰯」は猫がうたった詩になった。現在では、この夫婦はお金がなくて鮪が食べられなかったこと、また、ビキニ環礁で水爆実験が行われていた当時、海のものを食べることが控えられていたことなど、理解できるようになったこともあることはあるが、それでもやはり、なにか違和感が残る。簡単な単語で構成され、一見すぐに分かるような詩であるにもかかわらず、なにかが分からない、核心が掴めない。わたしはながい間、この詩人の詩を理解できずにいるような気がする。
本稿では、このような、かたちを捉えることの難しい貘の詩を深く読むことによって、言葉にできないこの詩人の魅力は、どのようにかたちがないのか、一体、なにを捉えることができないのか、を読みとくことで、「見えないもの」のかたちをみていきたい。
貘の「かたち」をひも解く道筋として、第1章で貘の経歴を、第2章で人間のなかにおける貘の生きる位置を見たうえで、第3章では貘の内面に迫る行為として「詩」と「貘」との関係性を考察し、第4章では貘のもつ「ユーモア」と言われるものから、その批評精神を探っていく。
1 『山之口貘全集』第1巻、思潮社、1975、247頁、以下、『全集』1巻、と略記する。
2 高田渡、大工哲弘ほか……『山之口貘をうたう』B/Cレコード、1998
1.山之口貘の道
貘の詩を読み進めるために、貘の人生の「道」を追うことからはじめる。わたしが余計な言葉をはさむまえに、貘自身から自己紹介をしてもらいたい。
ここに寄り集まつた諸氏よ/先ほどから諸氏の位置に就て考へてゐるうちに/考へてゐる僕の姿に僕は気がついたのであります/僕ですか?/これはまことに自惚れるやうですが/びんぼうなのであります
「自己紹介」3
「びんぼう」という言葉ほど、この詩人に付いて離れない言葉はない。「貧乏に生き、貧乏に死んだ詩人」「精神の貴族」「自然人」、貘を語る言葉はさまざまだが、それらのどれもに、この「びんぼう」は付いてまわる。このような、個性的な印象を与えるこの詩人の人生もまた、個性的なものであった。貘の詩のほとんどが自身の「生」をうたったものであるように、彼の詩からその「生」を除くことはできない。まずは、貘の生涯をみていきたい。
3 『全集』1巻、98頁。
1-1.貘の生涯
山之口貘、本名山口重三郎は、1903年、300年続く沖縄の名家の三男として沖縄県那覇区に生まれた。銀行員の父重珍と母カマトと、7人の兄妹のなかでのびのびと育ったようだ。中学のころから、強い自我が芽生えはじめ、日本標準語施行のための方言札制度4が行われた当時、「罰札制度の規則にすねだし、意識的に方言を使い、わざわざ罰札を引き受けたりする」5ようになり、その罰札を便所に捨ててしまうような生徒だった。16歳頃から、恋愛に熱心になりはじめ、下級生の姉・呉勢(グジー)と結婚するために、ユタを利用して婚約までこぎつけるがその恋も破談となり、そのあたりから貘の放浪人生の精神が形成されはじめる。16歳で中学を落第してからは、学校とも疎遠になり、絵画に没頭したり、大杉栄の影響を受けて詩を投稿しはじめ、学校からは「要注意人物」としてにらまれるようになる6。
1922年、貘19歳のとき、美術学校に行くために東京へと上京するが、1カ月で中退した。家からの送金も途絶えたために、詩を書きながら知り合いの家を転々とするものの、1923年9月、関東大震災に遭い、一時帰郷する。沖縄に帰って初めて、父が退職後に手を出した鰹節製造業が失敗し那覇の家を売り払って、家族は八重山に移り住んでいたことを知る。親戚や知り合いに嫌煙された貘は仕方なく、那覇の公園や海辺で放浪生活を送っていたが、1925年23歳で再び上京。この年から本格的な放浪がはじまる。
25年から38年にかけて、書籍問屋、暖房屋、汲み取り屋、ダルマ船の鉄屑運搬業、鍼灸医学研究所、ニキビ・ソバカス薬の通信販売などのさまざまな職を転々としていた。そのため、夜は土管のなかや、公園や駅のベンチ、キャバレーのボイラー室等、折々の仮住まいの生活をし、初上京から16年間畳の上で眠ることはなかったという。この時期に書かれた詩が『思弁の苑』に収められることとなる。同じころ、出版社に勤める知人の紹介で、佐藤春夫に出会い、そこから草野心平、高橋新吉、金子光晴らと親交を深め、1936年、詩のための雑誌である『歴程』の同人となる。この雑誌は、草野心平ら詩人8名によって、1935年に創刊された。「エコールとしてではなく詩自体の常に新しい創造を目ざして個性の集りとしての『歴程』」と定められた詩壇の理念は、詩を党派の表明とみなさない、貘の詩作態度と共通するものであった7。
1937年、貘34歳の時、茨城県出身の安田静江と結婚し、38年には『思弁の苑』を出版するが、貧乏生活に変化はなかった。1939年には、東京府職業紹介所に就職し、この時から貘の人生において最も安定した時期となる。1944年の娘・泉の誕生とともに戦災を逃れて東京から茨城に疎開し、4時間近くかけて仕事場に通う生活を続けていた。しかし1948年には退職し、詩一本の生活に入る。そのことによって、不安定な経済状況に再び戻ることとなる。その頃、疎開先から東京都練馬区貫井町の月田家に6畳1間を2ヶ月間の約束で間借りするが、結局亡くなるまでの16年間をその場所で暮らすこととなる。
1958年、55歳の貘は、34年ぶりに沖縄へ帰郷し、2ヶ月間滞在する。しかし故郷・沖縄のあまりの変貌ぶりに、半年ほど鬱のような状態になっている8。その後も体調は悪化するが、入院費用も手術代もなく、貘を慕っていた朝日新聞調査部の土橋治重が奉仕帳もって、佐藤春夫を筆頭にさまざまな人々からカンパを集め、その費用をもとに入院する。1963年闘病の末、胃癌により永眠する。59歳であった。
4 方言を口にすると罰札を渡されそれをそのまま持っていると繰行点一点減点となるもので、方言使用者をみつけてはその罰札をバトンするというもの。
5 「方言のこと」『山之口貘全集』第4巻、思潮社、1976、248頁、以下、『全集』4巻、と略記する。
6 「年譜」『全集』4巻、396-403頁、以下、この年譜を参照する。
7 『歴程』の基本理念には、「つくり出されるとそのまま古典であるようなそんな詩の、それをなし得るような新しい未知の詩人の発表の場とに歴程がなることが出来たなら、われわれの最も光栄とするところであります。〔中略〕われわれはわが国の詩を、常に世界的立場に於て思考し、旗も党も雑誌としては持たず、詩自体のなかに没入します」と書かれている。伊藤新吉『現代詩鑑賞講座』第8巻、角川書店、1969、437頁、以下、『現代詩鑑賞講座』と略記する。
8 貘の娘の山之口泉は帰郷後の貘をつぎのように語っている。「父は、帰るべき故郷を、その34年振りの帰郷の際に、皮肉にも、完全に失くしてしまったように思えてならない。父の故郷は、死んでしまった。父自身もまた、その時点から徐々に死にかけていたのだと言ってしまって過言でないような気がするのである」山之口泉「沖縄県と父・など」『山之口貘詩集』(現代詩文庫1029)、思潮社、1988、152頁
1-2.詩の特色
40年あまりの詩人人生のなかで、山之口貘が生涯に発表した作品は、およそ200編であり、これは詩人としてはかなり少ない。その少ない作品のなかでも、結婚を境にして前期と後期に分けることができる。前期の作品郡は、貘の第一詩集である『思弁の苑』(むらさき出版部、1938年)と、それに12篇を新たに加えた『山之口貘詩集』(山雅房、1940年)、再び訂正をした『定本山之口貘詩集』(原書房、1958年)が生前に発表された3冊であるが、後の2冊は、『思弁の苑』に加筆を繰り返したものであるため、生前に出された詩集は、実際には1冊であったといえる。これらの詩は、貘が放浪生活をしていた1923年から38年にかけて書かれたもので、この時期の作品を、貘の詩における前期の作品と呼ぶことができる。後期の作品は、結婚をし、その身を一定の場所に置くこととなった時期である、1939年から63年に書かれたもので、それらの作品は、死後、出版された『鮪に鰯』(原書房、1964年)に収められている。
前期と後期の作品は、その生活スタイルの変化から、詩にうたわれる内容の特徴にも変化がみられる。前期の作品には、野宿生活をしていたことから「僕」という存在を中心に、自身の存在への違和感や女性をうたった詩など、貘の安定しない、存在の浮遊感を伺わせる詩が多く作られている。また、前期でうたわれる貧しさには、貘ひとりの貧しさからくる、あきらめともいえる、身ひとつの気楽さのようなものが漂う。
後期の詩には、その身を「家族」という固定した場所に置く生活スタイルから、家族や、故郷・沖縄をうたったものなど、貘のいる位置が想像できるような、具体的な内容となっている。「貧乏」についても、身ひとつの貧乏の気楽さは消え、自分以外の「生」と生きる精神的な緊張感が存在する。前期の貧乏が肉体的な貧乏ならば、後期のそれは、精神的な貧乏だったともいえるが、このことは、肉体的・精神的貧しさというものではなく、貧しさからの肉体・精神への威圧ということができるだろう。肉体・精神が削られるのではなく、貘そのものは変化せずに「貧乏」に追いつめられ、肉体・精神が、居場所をなくしてしまう「貧しさ」である。
これら特色の異なる作品のなかで、本稿では『思弁の苑』を中心に、前期の作品を扱う。前期/後期と分けて読むことのできない、個々の魅力が貘の詩には存在するが、そのなかでも、わたし自身が、前期の作品に惹かれるものが多くある。それは、わたし自身の年齢が、貘が前期の詩を書いていた時期の年齢とほぼ重なっているからかもしれない。前期の作品には、推敲を重ね、磨きあげられた言葉によって、自身の存在への煮詰まることのない違和感が表現されている。同様にわたしも、自身の存在の浮遊感や、漠然とした自身の可能性へのあこがれなど、「若さ」ゆえの自分でも歯痒くなるような「捨てきれない」ものを引きずって生きている。その歯痒さ、「青さ」とも呼ばれるものが、前期の詩には濃厚に存在している。
1-3.詩への評価
『思弁の苑』を出版した当時の貘の詩への評価は、詩という表現の潮流に鮮烈な印象を与えるような華やかなものでは、決してなかった。『思弁の苑』出版後も変わらずに、作品を作るのみでは生きていけなかったことからも、貘の詩が当時の「大衆」に受け入れられていなかったことは確かである。その一方で、佐藤春夫や金子光晴などの一部のコアな人々には着々と受け入れられると共に、年代を追い、人々のなかにものごとを考える精神的な余裕が与えられるに従って、貘の詩が認識されはじめる。
戦後になると、人々の「沖縄」への関心や、社会の経済的発展に伴った一部の豊かな階級の人々の「貧しさ」を特別視する視点から、貘の存在も特別視されはじめ、テレビや雑誌などで度々、沖縄の文化や自身の貧乏生活について語る存在として知られていた9。しかし、その貘を見るほとんどの人々が、貘の存在を当時の「大衆」の「生」としてみるのではなく、「沖縄」や「貧乏」などのもの珍しいものでもみているかのような、エキゾチックな存在への興味として、認識していたようだ。
そのことからも、貘を語る一般的見解として、その詩が「大衆」の声であったことに視点を置いて語られるのは、貘の晩年の1950年代後半からのことであった。その新たな認識の代表的な例として、おなじく『歴程』の同人であった伊藤新吉は、1963年に出版された『現代詩手帳』において、貘が斜視の人生論を形成していると述べたうえで「斜視の人生論はそのどこかに批判的認識を付随する。それが現実感覚、庶民感覚となって作品を染め、世をすねたような、独特の人生的視野を形成する」と語っている10。このことからも分かるように、貘の詩への論考が本格的に行われたのは、貘の死後のことであった。
現在では、フォークシンガー・高田渡が貘の詩を歌った影響もあり、一部の若い人々のなかでは知名度のある存在になっている。高田渡のデビュー曲でもある「自衛隊に入ろう」などの曲からも分かるように、高田渡の諧謔めいた言葉からうまれる、社会への批評の精神は、貘の批評精神と重なるものがあり、高田渡はその重なるものに貘の魅力を感じ取っていたものと考えられる。文学の世界でも「沖縄」をうたった詩人としてのある程度の知名度はあるが、しかし「貘」そのものを論じたものは数えるほどしか残されていない。その貘を論じたものも「東京の根無し草の生き方との同時代的興味」として考察した竹内清己や11、「貧乏」「結婚」「文明」「沖縄」などのキーワードから貘の軌跡を探った仲程昌徳のように12、その「人生」に焦点をあてた研究が多く「詩」を中心に語られることは少ない。
本稿では、焦点を当てて語られることの少ない「詩」そのものの言葉を深く考察することを基本に、貘のかたちをみていく。ここまで、貘の概略を追ったが、このような位置に立った貘が具体的に人間のなかでは、どのような位置に立っていたのかを次章からみていきたい。
9 貘は度々、テレビや雑誌で、金子光晴などと貧乏対談をしたり、「沖縄」を特集した番組に「沖縄」を語る存在として出演していた。
10 『現代詩鑑賞講座』184頁
11 竹内清己「山之口貘―地球の詩人―」『国文学 解釈と鑑賞』1984、59巻、5号、69頁
12 仲程昌徳『山之口貘・貘とその軌跡』法政大学出版局、1975
2.貘の位置
2-1.貘の「尖り」
眠れないのである/土の上に胡坐をかいてゐるのである/地球の表面で尖ってゐるものはひとり僕なのである
「立ち往生」13
野宿生活をしていた当時の貘は、自身の生きる位置をどのように捉え、現実にはどのような位置を生きていたのだろうか。まず、ここにあげた「立ち往生」をもとに、貘の生きる位置を読みといていきたい。この詩は、貘が放浪を始めた当初の1923年頃に書かれたものである。当時の貘の詩には、土のうえで眠る行為を繰り返す「自然」のなかに放り出された貘と、しかし現実には「なお、寝る場所だけは、屋根の下に求めたいのだ」14という願望を諦めきれない貘の「現実」対「求めるもの」との狭間での定着できない浮遊感がうたわれている。
「尖っているもの」と、自身をまるで地球のなかの異物であるかのように表現しているところからも、自然のなかにおける自己の存在の疎外感をみることができる。1923年から38年の時期に放浪生活を送っていた貘は、親からの送金も途絶え、仕事も見つからず、土管のなかや、公園などで眠ることが多くあった。屋根の下で眠るという「一般的な」人間の営みを送れずに、人間から疎外された感覚を強く持っていた貘であったが、しかし、野外での生活も、満足に馴染むことができるものではなかったようだ。当時の貘は、さまざまな肉体労働を経験しているが、それらのどれも、長く続けることはしていなかった。どこか神経質な性質をもつ貘は、それらの仕事への嫌悪感というよりは、肉体労働の世界に、完全に馴染むことのできない貘自身に染み付いた性質のようなものが抵抗していたのかもしれない。貘は度々「人間の底辺」を生きた詩人であったと語られているが15、大正末期における「最下層」の人々の代表として、貘の存在をみることには違和感が残る。その当時の「最下層」の人々は「乞食」や「細民」と呼ばれ、頼れる知人もなく、通りすがる人々に金品を乞うたり、残飯を食べることで生きていたようであるが16、貘の言葉に、そのような貧しさが表現されていないことからも、貘の位置は決して「底辺」などではなかったように考えられる。しかし、その当時の「貧乏」は現代の「貧乏」とは比べものにならない貧しさであったことは確かである。
当時、土のうえで暮らすのは、近代化に伴って都市に流入したものの、屋根の下で眠る資本を持つことのできない、肉体労働者の人々であった。その外見は、つぎ布を当てた作業服などを着用した肉体労働者と、スーツを着用した「俸給生活者」「腰弁」などと呼ばれる人々などの、ひと目で階級がわかるような服装をしていたが、当時の貘は、もらいもののスーツやアルパカのコートを一年中着ているような、くたびれた「腰弁」のような服装をしていた。肉体労働の社会にも完全に馴染まなかった貘は、友人、知人から貰った服を着、詩の原稿用紙を肌身離さず持ち歩いていたため、そのかばんはいつも、意味ありげに膨らみをもっていた。実のところ、このような貘の風貌は、当時盛んな盛り上がりをみせていた社会主義者の風貌そのものであり、そんな彼が路上で眠っていると、警察に不審尋問をされることは避けられなかったようだ。そのため貘は、不審尋問を避けるかのように、あるいはなにか用事があるかのように、一晩中歩いていたという17。当時の貘からは、人間としての営みから疎外されながらも、誰かに見張られている緊張感や、風の音、寒さなどによる孤独感によって、土の世界にも完全に溶け込むことのできない、外的な力からの「尖らされた」存在であったことがわかる。
ここでもう一篇、自然にも人間にもなれない中間的な貘の存在を読みとることのできる、1935年頃に書かれた「夜景」をあげてみたい。
あの浮浪人の寝様ときたら/まるで地球に抱きついて ゐるかのやうだとおもつたら/僕の足首が痛み出した/みると、地球がぶらさがつてゐる
「夜景」18
この詩は、「浮浪人」「僕」「地球」という3つの関係から構成されている。先に述べたように、この詩は、眠る場所が見つけられず、夜通し歩いているときの状況をうたっているようであるが、詩の関係性を細かくみていくと、まず、地球に抱きついているようにみえる土の上での生活に適応して行く人々「浮浪人」と、それに対して、そちら側にも入ることができずにそれを眺める「僕」が存在している。この眺められる「浮浪人」は貘自身ではないにしろ、すくなくとも限りなく貘に近い人間であり、貘がこれから行こうとしている位置を指していることは確かだろう。その点からみても、貘はこの「浮浪人」に、自身の姿を投影しているとみることができる。
このような貘の足にぶらさがる地球は、彼にとってどのような存在なのだろうか。屋根の下で生活をする人々を人間の側、土の上で暮らす人々を自然の側とみるならば、「地球」という存在は自然の側であり、貘が自身の姿を投影している「浮浪人」の側であるとみることができる。そのことからも、自然と人間とのあいだの中間的な「尖った」存在である貘の足に「ぶらさがる」地球の行為は、貘を自然の世界へと引っ張るものであった。
自然の重力によって痛みだしたその足で、その重力を必死にこらえる貘は、人間の世界におおきな比重を置いていた。そもそも貘は野宿生活を興味本位に「体験」していたのではなく、当時の多くの人々が抵抗する術を持たなかったように、彼もまた、有無を言わせぬ大きな力によって、自然の生活の方へ押し流されていた人間であった。できることならば、一刻もはやく岸に揚がりたい……そんな感情を持ちながら、ぎしぎしときしむ地球の重力に、必死に耐えていたのではないか。
このように、中間的な「尖った」存在の貘であったが、ひとことで「尖った」といっても、その「尖り」にもさまざまな種類がある。なめらかな場所に木が一本生えているような異物的な尖りと、かたまりで存在していたものが、年月によって削られ、突出ななにかが浮かび上がるような、化石のような残された尖りと、尖りの在り方によってそのものの位置は変化してしまう。貘の場合、彼が沖縄という「異国」と見られていた土地から来たことや、土のうえでの生活を余儀なくされていたことなど、貘の意思とは反する異物的な、「尖らされた」尖りがあるが、他方、貘の意思としての意識的な尖りも存在している。ずいぶん昔からそこに存在し、ちょっとした震動や雨風にはびくともしない、むしろそれらによって一層、磨きかけられ、自身の存在を確立していくような遺跡のような尖りである。たとえば「数学」という詩からは、自らの意思としての「尖り」を明確に読みとることができる。
安いめし屋であるとおもひながら腰を下ろしてゐると、側にいた青年がこちらを振り向いたのである。青年は僕に酒をすゝめながら言ふのである/アナキストですか/さあ!と言ふと/コムミユニストですか/さあ!と言ふと/ナンですか/なんですか!と言ふと/あつちへ向き直る/この青年もまた人間なのか!まるで僕までが、なにかでなくてはならないものであるかのやうに、なんですかと僕に言つたつて、既に生まれてしまふた僕なんだから/僕なんです
「数学」19
「アナキスト」でも「コムミユニスト」でもなく「僕なんです」と主張するこの詩には、党派として人間が分かれていた時代にたいする「僕」というひとりの人間からの強い抵抗をみることができる。貘と同時代に生きた、作家の井伏鱒二(1898-1993)もまた、時代の潮流に乗ることのできない、流れから取り残された「尖った」感覚をつよく持っていたようだ。例として、井伏が1929年に発表した短編「山椒魚」の一節をあげてみたい。
多くの目高達は、藻の茎の間を泳ぎぬけることを好んだらしく、彼等は茎の林のなかに群をつくって、互いに流れに押し流されまいと努力した。そして彼等の一群は右によろめいたり左によろめいたりして、彼等のうちの或る一ぴきが誤って左によろめくと、他の多くのものは他のものに後れまいとして一せいに左によろめいた。若し或る一ぴきが藻の茎に邪魔されて右によろめかなければならなかったとすれば、他の多くの小魚達はことごとく、ここを先途と右によろめいた。
「山椒魚」20
自分の巣穴から出られない山椒魚が、右に左によろめく目高たちを眺めるこの場面について、加藤典洋は、「この時期、新思想に走らないばかりに一人もとの場所に残された小説家の悲哀を、心に残るしかたで定着している」と井伏自身の心境を述べているが21、貘の場合、そのことに「悲哀」を感じていたかどうかは別として、井伏と同様、意識的に取り残されたひとりであった。貘が放浪していた大正末期から昭和初期にかけては、詩の世界にマルクス主義の流れがうまれはじめた時代にあたる22。周りの人間が右に左によろめいていた時代に、潮の引いた浜辺に残った石のように「尖った」存在としての当時の貘の姿が想像できる。
このことからみても「貘」というひとつの尖った存在のなかに、肉体的な「尖らされた」ものと、精神的な「尖った」尖りとの2種類の尖りを内包していたことがわかる。このような貘の詩からは、人々のなかから人間をみるのではなく、意識的に「尖った」場所から人々を眺め、また、強制的に「尖らされた」場所から自身を眺めるという、2つの視点から、自身とそれ以外の人間の「生」がうたわれている。
時代の潮流からはみ出し「尖った」存在としての貘であったが、その「尖り」を外部から乱されることなく、「貘」という位置を維持させていたことには、なにものにも動じることのない精神の「つよさ」があったのではないか。その精神がどのように守られていたのかを、つぎに考えていきたい。
13 『全集』1巻、99頁
14 「貘という犬」『山之口貘全集』第2巻、思潮社、1975年、209頁、以下、『全集』2巻、と略記する。
15 伊藤信吉は「人生のいちばん底の方で、街の裏通りで、ボロのように寝ている者たちの飢餓感。そのとき山之口貘とそのまわりの人たちは、誰彼の差異なく、人生におけるボロになっていた」と語っている。『現代詩鑑賞講座』189頁
16 武田知弘『戦前の日本』彩図社、2009、176頁
17 「歩いて行く先々で、巡査や私服の刑事から、不審訊問を受けることが度重なって来たのである。」『全集』2巻、212頁
18 『全集』1巻、90頁
19 『全集』1巻、45頁
20 井伏鱒二『山椒魚』新潮社、1998、10頁
21 加藤典洋『日本という身体「大・新・高」の精神史』講談社、1994、174頁
22 「大正のほとんど末年、1926・7年のころになってようやくマルクス主義が詩の上にやや明瞭にあらわれてくる。〔中略〕文学運動は、ここで大きくプロレタリヤ文学運動としてかためられてくる」。中野重治『日本現代詩大系』第8巻・昭和期(1)河出書房、1951、494頁、以下、『日本現代詩体系』と略記する。
2-2.「柄」を着る行為
時代の潮流に乱されることのない「尖った」存在としての貘であったが、自身の精神における「生」はどのように維持されていたのか。詩人の茨木のり子は、貘についてつぎのように語っている。
貘さんを知っていた人たちは、みんな口をそろえて、かれのことを「精神の貴族」だったといっています。このことばがとても新鮮にひびくのは、「精神の貴族」といえるような人が、すくなくなり、それを目ざす人もまた、現代には見あたらないためでしょう23。
茨木のり子のいう「精神の貴族」とは、金銭的な貧しさに屈しない、貘の精神の豊かさを指しているようである。貘を語るうえで、この言葉がどれ程適切かどうかは別として、貘には、貧乏に屈することのない精神的なつよさが存在していることは確かである。その精神のつよさには、「精神の貴族」といった言葉から連想されるような高貴なイメージとは異なる、食いついて離れないしたたかさが存在する。「尖る」という言葉から連想される、他者を排除する「つよさ」ではなく、甲羅をつくり縮こまるような「耐える」つよさが貘のつよさである。1935年に書かれた「生活の柄」という詩には、そのような貘の「耐える」姿を読みとることができる。
歩き疲れては、/夜空と陸との隙間にもぐり込んで寝たのである/草に埋もれて寝たのである〔中略〕このごろはねむれない/陸を敷いてはねむれない/夜空の下ではねむれない/揺り起こされてはねむれない
「生活の柄」24
わたしたちは普段、「柄」という言葉を、どのように使っているだろうか。洋服の柄や、「ガラが悪い」「がらにもない」「土地柄」などと使ったりもする。その対象が場所であれ、人間であれ、イメージやジャンルを表すものとして使っているだろう。この詩のなかで、貘が使っている柄は、自身の生活においてのそれである。貘の生活の柄は、とにかく眠れない柄のようだ。野宿生活の柄では、寒くて眠れないのである。「この生活の柄が夏むきなのか!」とうたうこの詩からは、夏には夏の柄を、秋からは秋からの柄を、洋服のように季節に応じて着替えていかねばならない貘の生活を、窺い知ることができる。
大多数の人々は、衣替えのように季節に応じて生活を着替えて生きてはいない。人々にとって特定の生活は決まっており、季節など関係なくその生活を生きている。しかし、貘にとっての生活は、季節や人々に応じて着替えるものであった。寒くなれば、また違う柄を、土のうえで眠れないのならば、なにか、目的がある人間であるかのような柄を着てさ迷い歩き、友人に煙たがられれば、また、違う友人の柄へ……と、さまざまな場面で、さまざまな柄を着替えることによって、貘は生き、その行為によって、自身の精神を守り抜いていたのではないか。
たとえば、今着ている洋服の柄を見てみると、それはプリントされていたり、織り込まれていたり、いくら美しい柄であったとしても、わたしの体のなかまでは、入り込んでいない。柄を着る行為は、体を覆うことで寒さから身を防ぐためであり、すべてをさらけ出さないためのものである。「一般的」な人々が、自身を高めるために「柄」を着ているところを、貘は貧乏という「柄」を着ることによって、「貘」としての精神を守っていたのではないか。自身がどんなに惨めな存在になってまでも、精神を「守る」貘の行為には、精神を守りぬくことへのつよい執着が存在しているが、そのことは貘の「生きる」ことへの執着と重ねることができる。
ここまで、精神のなかにおける貘の「尖った」存在とそれを維持するための「柄」を着る行為についてみてきたが、次章では、このような位置に生きる貘の「生きる」ことへの執着とその「生」と「詩」との関係性をみていく。
23 茨城のり子「精神の貴族」『山之口貘詩集』(現代詩文庫1029)思潮社、1988、134頁
24 『全集』1巻、91頁
3.詩と貘
3-1.「喰う」行為
彼の執筆名である「貘」は、悪夢を食べるといわれる中国の架空の動物に由来する。そんな動物の「貘」らしからぬ貘もまた、人生のさまざまなものを食べて生きていた。
貘の「喰う」行為の対象は、食物ではなく、親、兄弟、友人、地球などのさまざまな人間や物体が対象になっている。
嚙った/父を嚙った/人々を嚙った/友人達を嚙った/親友を嚙った/親友が絶交する/友人達が面会の拒絶をする/人々が見えなくなる
「喰人種」25
この詩における「嚙った」は、「借りる」という言葉に変換することが可能である。住む場所もなく、その日暮らしをしていた貘は、なんとかその日の食事や、屋根の下で眠ることにたどり着く手段として、親、友人、兄弟からお金を借り、または、その夜を泊まらせてもらう「かじる」行為によって、その日その日を生きながらえていた。貘の詩には、人々に借りをつくって歩く自身の姿が多く表現されているが、貘はその行為のことを度々「喰う」と表現している。たとえば、「食いそこなつた僕」という詩には、つぎのように表現されている。
僕は、何を食ひそこなつたのか!/親兄弟を食ひつぶしたのである/女を食ひ倒したのである/僕をまるのみしたのである
「食ひそこなつた僕」26
このことからみても、貘にとっての「かじる」行為は、「喰う」という言葉に重ねることができる。さまざまな人を喰い、何度も友人、知人を訪ねていた貘は、しだいに嫌煙され、居留守を使われることもしばしばあったという27。先にあげた「喰人種」のなかで貘は、人々がじぶんから離れていく状況を「見えなくなる」と表現し、そんな自身の姿を「僕は/人情の歯ざはりを反芻する」と最後に表現している。じぶんの周りから消えてしまった人々の「人情」の歯ざわりを思いかえす貘にとっての「人情」とは、とても重い意味を持ったものとして、表現されていることがわかる。自身へのプライドや「人情」は、もはや自分で「喰って」消え去っており、貘は、そのプライドや「人情」の消え去った自己として、人々を喰って生きているのだ。彼にとっての「喰う」行為は、その行為によって、喰ったものたちを自身の肥しにするような、弱肉強食の構図ではなく「喰う」ことによって、自身が消え去り、各人に消化されていくような「提供」の「喰う」行為だったのではないか。貘は、自身がさまざまな人を「喰って」いることについて、つぎのように語っている。
おもえば、単に、図々しいばかりでは、そのような迷惑のかけ方は出来ないのであって、ましてや悪人と見做された人間などの、到底出来ることなのではなかったのだ。云わば、ぼくという人間は、自分の善良や温良に乗じて、意外にも図々しく生きているところがあるのではなかろうか。28
この言葉は、度々、不審尋問を受けることに悩んでいた貘に、佐藤春夫が自身の名刺の裏に書いて渡した「山之口君ハ性温良。目下/窮乏ナルモ善良ナル市民也。」という文句から浮かんだもののようだ。貘は、とても穏やかな人間であったと度々語られているが29、貘自身が、「温良」さや「善良」さを自覚し、そのような自己を提供することによって、「喰う」行為が成立していた。
貘にとって生きることと人々を「喰う」こととの比重は、お互いが引っ張りあっているかのように、比べることのできない重みがあり、彼にとって生きることとは、その、生きることと同じ重みを伴う「喰う」行為をしてまでも、執着しているものなのである。しかし貘の生きる現実は、もはや自身は「喰って」消えており、自分自身が生きることよりも、ただ「生きる」ことのみがひとり歩きしているようにみえる。そのように、自身を喰い、人々を喰ってまでも執着している「生」と貘とを繋げるものはただひとつ「詩」の存在のみであった。さまざまなものを「喰って」いた貘の「生」への執着は、「詩」への執着ということができる。
貘にとっての「喰う」行為には、なにごとにも変えがたい、詩から導かれる生きることへの執着が感じられる。さまざまな人々や自身を喰ってまでも、生きることや詩にしがみつく、そのしたたかさには、自身に対する冷酷さがある。「貘」というひとつの存在の意思を無視し、「詩」に喰いついて離れない姿を想像させるような、ある種の恐ろしい一面を貘は根本に持っているのではないか。貘には、詩と自己との繋がりへの揺らぐことのない確信があった。その確信によって貘は「喰う」行為を繰り返し、生きていたようである。
25 『全集』1巻、96頁
26 『全集』1巻、52頁
27 「世木にしても高円寺の友人にしても、度重なるぼくの行為に対しては、あるったけの同情は出し尽くしてしまったのであろう。このごろでは、玄関先で、かれの名を呼んでも、返事さえも出てくることがなくなったのだ。」『全集』2巻、203頁
28 「貘という犬」『全集』2巻、219頁
29 金子光晴は貘のことを「貘さんという人はひどくしずかで、スロモーで、用心ぶかく、おちついていて、親切で、そのうえ、一段とユーモアのある人だ」と語っている。金子光晴「山之口貘のこと」『金子光晴全集』第13巻、中央公論社、1976、291頁
3-2.「詩」と「生」
詩を書くことよりも まづ めしを食へといふ/それは世間の出来事である/食つてしまつた性には合はないんだ/もらつて食つてもひつたぐつて食つても食つてしまつたわけなんだ/死ねと言つても死ぬどころか死ぬことなんか無駄にして食つてしまつたあんばいなんだ〔中略〕めしに飢えたらめしを食へ めしも尽きたら飢えも食へ飢へにも飽きたら勿論なんだ/僕を見よ/引っ越すのが僕である/白ばつくれても人間顔をして 世間を食ひ廻はるこの肉体を引き摺りながら 石や歴史や時間や空間などのやうに なるべく長命したいといふのが僕なんだ
「転居」30
この詩は、貘がダルマ船に乗って鉄屑運搬業をしていた、1936年頃に書かれた詩である。「詩を書くことよりも まづ めしを食へ」という言葉は、当時の貘が度々浴びせられていた言葉であった31。当時の人々には、人間を「喰って」までも詩にしがみつく貘の姿が、あまりにも滑稽に映っていたことだろう。そのような言葉を「それは世間の出来事である」と一括してしまう貘からは、それらの言葉はまったく自身に関係のないものとして存在し、とにかくなにを喰ってでも詩を書くために「生きる」ことのみが、重きを置いて主張されている。しかしその「生きる」ことへの意思には、諦めのような気楽さが漂い、「生きる」意思さえも他人事のようである。自身の「生」と「詩」との関係について、貘はつぎのように語っている。
しかし、上京はしたものゝ、すぐにはどうにもなる筈がなかった。しばしば、自殺をおもひ立つのであつたが、そのたびに詩は未練がましく、もう少し書きたいといふ気持をどうすることも出来ないで、とうとう自殺をしたつもりで生きることに決めたのである。この決心は、ぼくから、見栄も外見も剥ぎとつてしまつて、色々なことをぼくにさせることが出来たのである32。
「自殺したつもりで生きる」という言葉からもわかるように、貘は「詩」に導かれることによって「生」を維持した詩人であった。このような詩への姿勢からは、自己などはすでに超越し、「詩につかまった」逃れられない貘と詩との関係性をみることができる。貘は、その個性的な生き方を抜きには語ることのできない、自身の「生」をうたった詩人であったことから、詩自体の評価も生き方と共に語られ、「独自性」や「個性」の強い詩人であると考えられている。だがその「独自性」が現れるのは「詩」のなかにおいてではなく、その「生き方」においてであり、「生き方」の独自性と「詩」の独自性とが混同されてしまうことが多くある。「詩」のために生きた自らの「生」をうたった貘の生き方は極めて個性的であったが、肝心の「詩」と貘との関係性は、惨めなまでに「自己」を制圧し、その自己を「詩」に提供することによって存在するような、「個性」と呼ばれるものとは相容れないものだったのではないか。
貘の「詩」には「詩」と「貘の詩」という2種類の「詩」が存在している。先にも述べたようにまず「詩」の存在に導かれるかたちで貘の「生」が維持され、その「貘」が生きることによって「貘の詩」がうまれるという関係性である。「詩」が貘の意思に関係なく導かれるものならば、「貘の詩」は、その導かれたものから派生する貘の意思のようなものであるといえる。伊藤新吉は、貘の詩について、「生活や人生をどこかへ放り出してしまいたいというような、それでいて生の低の方にへばりついているという、そういう否定と肯定との2つの姿勢が、矛盾することなく重なっている」と述べているが33、確かに貘の詩には、世の中への諦めのようなすねた姿勢がある一方で、その行為によって、なにかを深く批判しているような、頑丈な意思が存在する。このような一見、矛盾する行為が、ひとつの繋がりとして認識できることには、貘のなかの2つの詩の存在、そしてそのあいだにある「貘」の存在が絶妙なバランスを持ち、橋渡しをしていることが重要なのではないか。
では、詩のなかにおける貘の「生きる」位置とは、どのような位置にあるのか。その位置を理解するためには、先にあげた「転居」のなかの一節が重要になる。「石や歴史や時間や空間などのやうに なるべく長命したいといふのが僕なんだ」とうたうこの言葉は、貘そのものを表現しているかのような、彼らしい「生」への執着が感じられる。その執着は、「石や時間のように長生きしたい」といった単純な願望ではなく、誰も管理することのできない「時間」を、自らの存在によって管理してしまっている、「石や歴史や時間や空間」に対する、それらが内包する、時間の超越性への貘自身の共感と呼ぶことができる。
貘の娘である山之口泉は、貘と時間との関係性についてつぎのように語っている。
時間は、父にとって、無限に自分のものだったように見える。たった五十九年ぽっちの短い生涯ではあったけれど、実は、何百年、何千年、何万年という果てしない時間を、ちゃっかり所有していたのではないか34。
たしかに、貘の「生」の在り方には、貘自身があげた「石」「歴史」「時間」「空間」といったものたちの在り方と重なるものがある。重なるものとは、まず、それらのどれもが、自身が時間軸となり存在することによって、それら以外の繋がりへの土台となり媒体となっていること。そして、媒体となることによって、時間軸から解放され、第三者的視点から、ものごとと自身を眺めている点である。「詩」のなかにおける貘もまた「詩」と「貘の詩」との間接的な位置に自身を置くことによって、ひとつの「詩」を形成させている。このように、本来ならば「矛盾」と呼ばれるような関係性が、違和感なく成り立っていることについて、伊藤信吉はつぎのように述べている。
だが、そんなふうにちぐはぐであるからこそ、ここでは人生というものが危うく形を成しているのだ。これをきちんとした形にまとめようとすれば、山之口貘の人生の足場は、ばらばらに解体してしまうかもしれない35。
この言葉は、鋭い指摘である。まさしく貘の位置は、矛盾の塊のような関係性のもとに存在している。本来ならば、相容れないものたちが、反発しあって崩れるところを、貘は、そのことによって互いを維持し、「貘」という独自の位置を確立している。「貘」というひとつの存在ではなく、「詩」と「貘の詩」という、いくつもの視点を持つ「貘」の位置からうたわれた貘の「詩」には、どこか矛盾しているようで、そのことによって核心を見つめているような鋭さがある。貘の内包するさまざまな視点の重なりが、ものごとの根底を見つめる「鋭さ」となっているのではないか。
このように、「貘」はひとつの存在としての「貘」ではなく、繋がりとしての「貘」という独自の位置を維持していた。その位置にいる「貘」は社会とどのような繋がりを持ち、どのような思想を持っていたのか。次章では、貘の社会的な思想性について探っていきたい。
30 『全集』1巻、33、34頁
31 「或る日のこと、斎藤さんは詩人のことに就いて僕に相談を持ちかけてきた。〔中略〕彼は僕に、詩人をやめますかそれとも職をやめますか、と、まるで子供に玩具を与えるようにそう言った。」『全集』2巻、53頁
32 「詩とはなにか」『全集』4巻、78頁
33 『現代詩鑑賞講座』193頁
34 山之口泉「沖縄県と父・など」『山之口貘詩集』(現代詩文庫1029)思潮社、1988、144頁
35 『現代詩鑑賞講座』194頁
4.時代と貘
4-1.時代性
山之口貘の前期の作品に共通している特徴としては、時代背景の希薄さが挙げられる。後期の作品では、故郷である沖縄の変貌と喪失への悲哀を表現した詩が残されているが、前期の作品には、貘個人の人生や生活を想像させる詩が大半を占め、それらの詩から時代背景を読みとることは困難である。時代性がかすみ、貘個人が浮き彫りになって歩いているような、いつの時代であっても変わらずに、貘は貘の詩を書いていたであろうと感じさせるような、「僕」という個性を前面に出した詩人の姿をみることができる。
『思弁の苑』に収められた詩を書いた1923年から1938年の時期のみをみても、社会状況は激変している。1923年の関東大震災で東京は崩壊しており、その混乱に紛れて多くの朝鮮人や社会主義者たちが虐殺され、1929年には世界恐慌が起こり、日本は一直線に軍事国家へと突入していく。貘の身近な文学の世界でも、大正末期からプロレタリア文学運動が盛んになりはじめる。
中野重治は、当時のプロレタリア文学運動において、特にきわだった現象として、「まったく無名の人が大量にあらわれてきたことと、かつて歌われなかった生活風景がかつて歌われなかったような叙事詩的な形で歌われて来たこと」と述べたうえで「人々はそこで詩に目ざめて詩にすすんできたのでなく、生活に目ざめたことによって詩にすすんできた。詩は、いわば彼らが生活に目ざめたことの直接の証だったわけである」と述べている36。ここで、1926年に書かれたプロレタリア詩のひとつともいえる詩をあげてみよう。
底だ底底どん底だ/この世の底だ どん底だ/もし堤防が崩れたなら/瓦斯が爆発したならば/水攻め 火攻め その上に/天井がバレたら生き埋めだ/底の底なるどん底に/この世の底のどん底に/俺は炭掘る採炭夫
後藤謙太郎「採炭夫の歌」37
重治のいう「生活に目ざめた」詩を書く人々の場合、大正末期の時代において、ようやく自身の社会的位置や生活状況を見つめる、時間的、知識的な豊かさが与えられ、そのなかでの、自らの意思表示の媒体として、「生活詩」というものが立ちあがりはじめた。しかし、そのことを当時の貘の詩と重ねてみると、重治のいう当時のそれとはまた違ったものがある。貘は、詩のなかで、世の中における自身の考えや主張をせず、一貫して「僕」の世界とそれに影響を及ぼす人々を表現した。そのような、当時の貘の詩作への姿勢を読みとることのできる詩として、35年に発表された、「座蒲団」がある。
土の上には床がある/床の上には畳がある/畳の上にあるのが座蒲団でその上にあるのが楽といふ/楽の上にはなんにもないのであらうか/どうぞおしきなさいとすゝめられて/楽に坐つたさびしさよ/土の世界をはるかにみおろしてゐるかのやうに/住み慣れぬ世界がさびしいよ
「座蒲団」38
この詩については、「上京してから何年というほどに野外に住んでいた浮浪者のぼくが、就職の件で先輩の家を訪ねて、久し振りに座蒲団の上に坐ったのであったが、自分ながらあの頃の生活のかゆさがおもい出されるのである」と自らが語っている39。土、床、畳、楽と重なり、さて、そのうえにはなにがあるのだろうか。と、わたしたちに問いかけるこの詩からは、座蒲団という日常的な道具を通して、階級社会への違和感と疑問を読みとることができる。しかしこの詩から、当時の社会背景や彼の持つイデオロギーを読みとることは困難である。社会主義者達が、命をかけて反戦詩を書いていた時代に、座蒲団の違和感について黙々と書いていたこの詩人は、主張としてどこか生ぬるく、運動の最前線にいた人たちにとっては、ばかけた存在に映っていたことだろう。しかし、貘はそれらの詩を、ふざけ半分に書いていたのではなく、至って真面目に、全精神をつぎ込んで表現していた。そのことは、貘が、一篇の詩に百枚、二百枚と原稿用紙を屑にしなけば完成させることのできない、推敲に徹した詩人であったことを取っても確かである40。
貘が詩を投稿していた詩壇は、先にもあげた『歴程』の他に『改造』や『詩行動』などの左翼系の雑誌であり、また、中学時代の貘は、大杉栄などの影響を受け、人間の階級を石炭に例えた、教員にたいする批判詩を発表したりしている41。それらのことからみても、社会主義的な思想を持った人びととは、少なからず近しい思想を持っていたことがわかるだろう。また、社会主義者などが、思想弾圧を受けていた時代であったことから、政治的な発言を控えていたとみることもできるが、貘の場合、そのような配慮とはまた異なった意識が感じられる。そこには、なににもならない「僕」主義に一貫した貘の生き方からくる、意識的な、書かないことへの意思が存在している。
36 中野重治『日本現代詩大系』495頁
37 後藤謙太郎「労働・放浪・監獄より」『日本現代詩大系』10頁
38 『全集』1巻、41頁
39 「詩とはなにか」『全集』4巻、73、74頁
40 「おもえば、詩を書くようになってから、すでに、三十年余にもなるのであるが、ぼくは、いまだに、二百枚三百枚と推敲しなくては一篇の詩も書くことができないのだ。」『全集』4巻、38頁
41 貘は、1920年に、「石炭」という詩を、「琉球新報」紙上に「サムロ」の筆名で発表している。『全集』2巻、360頁
4-2.貘のもつ「ユーモア」
ここで、貘の「書かない」ことへの意思を読みとる手段として、貘が信頼を置き、親しくしていた詩人、金子光晴の詩「石」と貘の同題詩を比較してみたい。
土ぼこりで白い雑草の根方、/電柱や、道標の周りに、垣添ひに、/車輪に砕かれ、荷馬の蹄にはじかれ、/靴底にふまれ、下駄にかつとばされ/だが、誰もこころに止めないのだ。/君を邪険にあつかつたこと、君がゐることさへも。/たまさか、君を拾ひあげるものがあつても、/それは、気まぐれに遠くへ投げるためだ。
金子光晴「石」42
季節々々が素通りする/来るかとおもつて見てゐると/来るかのやうにみせかけながら僕がゐるかはりにといふやうに/街角には誰もゐない/徒労にまみれて坐つてゐると/これでも生きてゐるのかとおもふんだが/季節々々が素通りする/まるで生き過ぎるんだといふかのやうに/いつみてもここにゐるのは僕なのか/着てゐる現実/見返れば僕は/あの頃からの浮浪人
山之口貘「石」43
どちらの詩人も「石」を人間にたとえることによって、現実社会への違和感を暗示させているが、これらの詩には、その「石」をみる視点の違いからくる、問題意識の差異が存在している。まず、光晴の「石」をみる視点が第三者的な眺める存在にたいし、貘の場合、貘自身が「石」になり、それを眺める「僕」の視点からうたわれている。まるで、光晴が、貘をみて書いているかのような、みる側と僕という、ある意味で、意気投合した両者の作品が存在する。光晴が、大衆にたいする個人として、真正面から、ひろく、大多数の問題へと疑問を投げかけているのにたいし、貘の場合、まるで、貘個人の問題であるかのように、問題を個人の恥として、自嘲的に内在化してしまう。むしろ問題というよりも、読者に暖かな微笑みを誘うような、目の前にある苦しみや矛盾を、楽天的に変換してしまうような、癒しの効力をも伴っている。この詩には、「石」のように道端に転がっている「僕」にたいする怒りもなければ、「僕」を避けて歩く人びとや季節への怒りもない。ただ、その現実のみが存在し、「徒労にまみれた僕」が転がっている。
金子光晴は、自身の詩と貘の詩とのちがいについて、つぎのように述べている。
僕がまっ正面な抗議のような詩をかけば、彼は、日常のなかのユーモアでそれとなく反戦を仮託する。貘さんの反戦のイデーは、イデオロギーなどといういい加減な、反戦がすぐ好戦に変わるようなわがため主義からではなく、もっと、人間の本心に根ざして彼という個人から発したものであった44。
たしかに、貘の詩には「それとなく」の精神が充満している。「反戦」を「反戦」として表現することは決してせず、しかし、目の前にある個人の日常を、ただ、それとして表現することによって、それではない核心へと、「それとなく」導きかける。このような貘の詩の特徴を人々は「ユーモア」などと度々呼んでいるが、同様に「ユーモア作家」と呼ばれていた井伏について論じた亀井勝一郎の言葉には、貘の持つ「ユーモア」と重なるものがある。
しかし、ユーモアとは悲しいものである。悲劇よりも喜劇の方が悲しいと感じた人によってのみ描かれうるものである。そしてその根底にあるのは、人間観察、文明批評のきびしさだ。井伏さんの何げない描写の奥に、厳しい拒絶をみるべきである45。
貘の言葉にもまた、井伏と重ねることのできる「拒絶」がある。貘の言葉には「人間への愛」ではなく、人間への途方もない諦めと絶望が存在している。そのような人間への絶望を、自身の一部としてうたうことによって、貘の詩は人間の絶望としての「生」の姿を表現しているのではないか。貘の詩に、おかしみを感じて笑いはじめるか、後ろめたさを感じて黙り込むか、貘の詩の持つ意味は、読者に託されているが、貘はその読者にさえ、軽蔑を持って、突き放しているようなところがある。「そう易々と理解させてやるものか」という、詩にたいするプライドのような「ユーモア」を感じるのだ。
貘の詩には、言葉にすることのできない、巧みな引力のようなものが存在する。たとえば光晴が吠える犬になり、社会の構造などを、知識や知性に訴えかけてくるならば、貘の場合、いまある現実を、なんども熟考し、厳選された言葉にすることによって、読者の感覚、感情のなかに、小石を投げ込み、ちいさな波紋をうみだす。ひとことで答えてくれるような、明確ななにかは存在しないが、なんだか、もやもやするような、ちいさな傷を読者につけたまま、貘は去ってしまう。その傷は、うかうかしていると、楽天的な「癒し」などという感情に包み込まれてしまう、かすかなものではあるが、そのかすかな傷には、後ろ髪を引っ張っぱられるような、捕らえたら離さない、執拗さが伴う。貘は、明瞭な批判詩を書いた詩人ではなかったが、しかし、彼が根底に持っていたものは、社会に対する痛烈な批評の精神であった。彼はその根底にある精神を、そのまま言葉にするのではなく、何度も屈折させることによって、読者に「考える」ことを要求していたのではないか。
42 金子光晴『金子光晴詩集』岩波書店、1991、48、49頁
43 『全集』1巻、70頁
44 金子光晴「貘さんのこと」『金子光晴全集第十五巻』中央公論社、1977、444頁
45 亀井勝一郎「『山椒魚』について」『山椒魚』新潮社、1998、265頁
4-3.批評精神
ここまで、貘の詩には、時代背景が希薄であったこと、明確なイデオロギー詩を表出させていなかったことなどを論じてきたが、他方、貘の詩作において「社会」という存在は、廃除しては語れない重要な位置を示していたことも確かであった。
先にあげた、金子光晴の言葉からもわかるように、貘が自身のイデオロギーを詩に表出させていなかったことは、度々言われていることだが、米倉巌はそのことについて、それを認めながらも、「しかし詩が本来、批評精神ないし諷刺の精神をもっているものだということは、貘自身がつよく認識していたことであった」と述べている46。では、貘の持つ批評精神とは、どのようなものだったのか。そのことを理解するにあたって、『思弁の苑』のなかでも、とりわけ貘の思想性が表出されている、「鼻のある結論」を読むことからはじめたい。
ある日/悶々としてゐる鼻の姿を見た/鼻はその両翼をおしひろげてはおしたゝんだりして 往復してゐる呼吸を苦しんでゐた〔中略〕またある日/僕は文明をかなしんだ/詩人がどんなに詩人でも 未だに食はねば生きられないほどの/それは非文化的な文明だつた〔中略〕あゝ/かゝる不潔な生活にも 僕と称する人間がばたついて生きてゐるやうに/ソヴィエット・ロシヤにも/ナチス・ドイツにも/また戦車や神風号やアンドレ・ジイドに至るまで/文明のどこにも人間はばたついてゐて/くさいと言ふには既に遅かった
「鼻のある結論」47
この詩は、貘が汲み取り屋をしていた1937年に書かれた詩である。貘は、この詩について、「人類は鼻など持っているために、こんな臭い仕事とおもわないでもなかったのであるが、鼻をなだめすかして汲み取るより外には術もなかったのである」と語っている48。この言葉からもわかるように、貘の言葉には、ねばりがある。「こんな臭い仕事はいやだと思った」というその一言でさえ、「おもわないでもなかったのであるが」と屈折させ、一瞬、彼の主張を消してしまう。貘の詩は、ほとんどがその技法でうたわれている。
僕の鼻が「臭い」に苦しんでいる事実を「詩人がどんなに詩人でも 未だに食わねば生きられない」と、自身が汲み取り屋をして「食わねば」ならない現実と照らし合わせ、「文化」と「非文化的文明」との対立する性質に、板挟みにされた自らの位置を暗示させている。貘のいう「非文化的文明」とは、人間の文化、人間の自然発生的な意思を無視してうまれた文明、例えるならば独裁的な流れを持ちはじめた社会を示しているのではないか。そのような関心を「文明論」へと派生させ、さらにその「文明論」を「ソヴィエット・ロシヤ」や「ナチス・ドイツ」などの、社会的関心へと広げている。ここで挙げられる「ソヴィエット・ロシヤ」「ナチス・ドイツ」「戦車」「神風号」49「アンドレ・ジイド」50は、貘にとっての、「文明」の代名詞として挙げられていることがわかる。貘のいう「文明」とは、先に述べた、文化を無視して生まれた文明である「非文化的文明」を指しているようだが、例外的に「アンドレ・ジイド」のみは、「非文化的文明」ではなく、文明の本来あるべき姿として表現されていたことがわかる。「文明のどこにも人間はばたついてゐて」と表現する貘の言葉からは、自身の嗅覚である「鼻」が「非文化的文明」に翻弄されているように、人間の社会も同様に「非文化的文明」に翻弄されている姿を重ね合わせ、社会の独裁的・専制的流れを「嗅覚」という極めて個人的な視点から批評している。
このように「鼻」という、一見「文明」とはなんの関係のないようなものから「文明」の本来あるべき姿をみる貘の詩は、貘の生きる姿勢と重なるものがある。世の中が、思想性や党派でわかれ、多数派がものをいう時代において、「個」の視点から社会をみる貘の詩には、社会にたいする「感覚」としての違和感が表現されている。金子光晴は『思弁の苑』の序文のなかで「貘君によつて人は、生きることを訂正される。まづ、人間が動物であるといふ意味で人間でなければならないといふ、すばらしく寛大な原理にまでかへりつく」51と述べているが、確かに、貘の詩の頑丈さは、人間が本質的に根ざした「感情」や「感性」から発しているところにある。貘は詩のなかで、自身の思想や主張を表現するのではなく「僕」の現実をうたうことによって、その位置からしか表現することのできない「いま」を表現していたのではないか。そのような「貘」の視点からうたわれた詩には、時代の流れによって薄められることのない「貘」としての濃厚な色が現在でもみることができる。何十年も前に書かれた貘の詩が、色あせることなく、わたしのなかに響いているその理由は、その言葉が「僕」という個人から発せられていることにある。「僕」の視点から、さまざまなものをうたったその位置が、時代に消されることのない、濃厚な「いま」を維持する貘の詩のつよさとなり、現在でも詩が色あせることのないちからとなっているのではないか。
46 米倉巌「山之口貘の位置−第一詩集『思弁の苑』を中心に」『昭和詩人論』有精堂出版、1994、253頁
47 『全集』1巻、26頁
48 『全集』2巻、74頁
49 1937年に製造された航空機の名前。当時の日本における文明の象徴であったと考えられる。後の太平洋戦争では、陸軍や海軍においても使用されることとなる。「1937年、東京−ロンドン間の連絡飛行で、国産機による国際記録を樹立した、国産の二人乗り高速通信連絡機の名前。」『日本大百科全書』5、小学館、1985、711頁
50 「Andre Gide( 1869~1951)フランスの作家、個人主義的立場から既成道徳・宗教・社会制度を批判した」『広辞苑』第三版、岩波書店、1985、1017頁
51 『全集』1巻、20頁
5.おわりに
本稿を書くなかで、わたしが常に格闘していたものは、自身の「感情」であった。「論文」という形式や「論理的」にものごとを述べることに不慣れなわたしにとっての「論文」を書く行為は、いかに「わたし」を抑えるかという作業に近いものであったが、しかし貘の詩をみるなかで共通して浮かびあがってきたことは、詩のなかでの「貘」という強烈な主張と、「論理」では述べることのできない、かたちにならない貘の存在であった。「自然」と「人間」、「詩」と「貘の詩」、「右」と「左」、「夜空」と「陸」これら事物と事物との間に貘は存在し、その位置からの思想性もまた、貘の根本的な「感情」という、かたちにならないものからうまれている。このように、かたちにならない浮遊した存在の「貘」を表現したその詩から、なにかしらの秩序立てた筋道を見つけることに、わたしは違和感を振り払うことができなかった。わたしが「貘」になってはならない。そのような警戒心を持ちながら進めたこの作業であったが、結局のところ、わたしがこの論文を書く原動力となっていたものは、「論理」といわれるようなものと対抗する貘の存在への共感でしかなかった。事物と事物とのあいだにある名前のないもの、言葉にならないもの。わたしの生きる原動力はそこにあるのかもしれない。それは、貘のみにいえることではない。国境と国境のあいだにあるもの、男と女のあいだにあるもの、豊かさと貧しさのあいだにあるもの、夜と朝のあいだにあるもの。これら「ない」はずのなかに「ある」ものにこそ、ものごとの本来の姿が現れ、同時に、それらがもつ矛盾が凝縮されているのではないか。
本稿では、貘の詩を読みときながら、1章では、貘の生涯の流れを追い、2章では「尖った」貘の存在とその「尖り」を守るための「柄」を着る行為をもとに、人間のなかにおける貘の位置をみた。3章では貘の内面的な「生」と「詩」との関係性を探るために、彼の内面にある、「詩」「貘」「貘の詩」という3つの関係性を考察した。また4章では、貘の思想性を探り、彼の持つ「ユーモア」と呼ばれるものの存在と、その批評精神をみた。本論のはじめにも書いたように、わたし自身が貘の詩のどこに惹かれ、どのようなところに「かたち」のなさを感じているのかをさぐる行為として、ここまで進めてきたが、いま「貘」の「かたち」として浮かびあがるのは「尖り」としての貘の位置からうまれたであろう「冷酷さ」である。どこか、世の中をばかにしたような、自身の「生」などは投げ捨てたような「冷酷さ」が、貘の根本を形成しているのではないかと、今になっておもうが、その「冷酷さ」を表現する言葉を、ここまで書いた現在も、わたしは持ち合わせることができずにいる。
「冷酷さ」を考えるなかで、わたしのなかに、ある映画のシーンが思い出された(『レネットとミラベル/4つの冒険』)52。それは、主人公の少女が、夜と朝のあいだの「青い時間」をみるために、朝とも夜とも言えない時間に起き出して庭に立つ場面だった。庭に立って外の音を聞くただ、それだけの場面であるが、その「青い時間」には、朝の鳥は目ざめず、夜の鳥は眠りについた、だれもが眠った「沈黙」の瞬間があるのだという。たしかにその瞬間は、なにも「ない」瞬間だった。その「ない」場所には、「夜」や「朝」といった余計な観念が排除された、ただその「ない」瞬間のみの、広さのようなものが存在していた。主人公のレネットは、その「青い時間」をつぎのように表現している。
世界に終わりがあるとするなら、あの時間よ。自然が呼吸をとめるような気がする。とても怖いものよ。
いま、その場面を思い出してみると、「青い時間」は、まるで貘のようだと感じる。だれもが息を止めた瞬間。ほんの数ミリずれただけで、一瞬にしてすべてが崩れてしまうような、危うい「かたち」を持つ貘の存在には、世界の終わりの境界線を動じることなく直視しているような「冷たさ」がある。貘にとって、行き着く場所は、その境目しかなかった。貘が持ち合わせる「かたち」にならないものは、彼にとって、コンプレックスでしかなかったが、貘はその「かたち」がないというコンプレックスをそのまま「詩」にすることで、自身と世の中の「かたち」をみていたのではないか。
世の中には、自分の意思でそうなったのではなく「こうなるしかなかった」という追いつめられた状況のもとでうまれる、さまざまな「かたち」にならないものがあるようにおもう。その、かたちにならないものにこそ、わたしたちがみるべき「かたち」があるのではないか。「見えないものをみる」とは、そのような行為をいうのではないか。
わたしは「かたち」にならなかったもの、視覚に映らなかったものを、みることのできる目を持っていたい。「みえる」のを待つのではなく、「みる」行為を意識的に行っていかなければならないのだとおもう。
52 Eric Rohmer 『レネットとミラベル/4つの冒険』シネセゾン、1986
参考文献
単行本
・山之口貘『思弁の苑』むらさき出版部、1938
・山之口貘『山之口貘全集』全4巻、思潮社、1975-1976
・山之口貘『山之口貘詩集』(現代詩文庫1029)思潮社、1988
・山之口貘『永遠の詩③山之口貘』小学館、2010
*
・伊藤信吉『現代詩鑑賞講座』第8巻、角川書店、1969
・茨木のり子『うたの心に生きた人々―与謝野晶子、高村光太郎、山之口貘、金子光晴』さえら書房、1967
・井伏鱒二『山椒魚』新潮社、1998
・荻原昌好『少年少女のための日本名詩選集』9、あすなろ書房、1986
・加藤典洋『日本という身体「大・新・高」の精神史』講談社、1994
・金子光晴『金子光晴全集』第13・14巻、中央公論社、1976-1977
・金子光晴『金子光晴詩集』岩波書店、1991
・佐藤春夫「放浪三昧」『定本 佐藤春夫全集』第10巻、臨川書店、1999
・笹沢美明、他『日本詩人全集』33、昭和詩集(1)、新潮社、1969
・高良勉『僕は文明をかなしんだ』彌生書房、1997
・武田弘『戦前の日本』彩図社、2009
・中野重治『日本現代詩大系』第8巻、昭和期(1)、河出書房、1951
・仲程昌徳『山之口貘・貘とその軌跡』法政大学出版局、1975
・山之口泉『父・山之口貘』思潮社、1985
・山之口泉・沖縄タイムス社『アルバム・山之口貘』沖縄タイムス社、2003
・米倉巌『金子光晴・戦中戦後』和泉書院、1977
雑誌
・竹内清己「山之口貘-地球の詩人-」『国文学 解釈と鑑賞』59巻5号、至文堂、1984
・米倉巌「山之口貘の位置」『昭和詩人論』有精堂出版、1994
その他
・高田渡、大工哲弘ほか……『山之口貘をうたう』B/Cレコード、1998
・Eric Rohmer 『レネットとミラベル/4つの冒険』シネセゾン、1986
profile
安藤春菜(あんどう・はるな)
1989年、長野県生まれ。
京都の大学を卒業後、京都と長野を往復しては、自らの人生を模索中。
目次
はじめに
山之口貘の道
1-1.貘の生涯
1-2.詩の特色
1-3.詩への評価
貘の位置
2-1.貘の「尖り」
2-2.「柄」を着る行為
詩と貘
3-1.「喰う」行為
3-2.「詩」と「生」
時代と貘
4-1.時代性
4-2.貘のもつ「ユーモア」
4-3.批評精神
5.おわりに
参考文献
いまからおよそ100年ほどまえ、山之口貘という詩人が生まれた。この詩人は、世の中が戦争の混乱によって緊張感を持ちはじめた1930年代の東京に生きながら、ろくな反戦詩も書かず、人間の混乱のうえをひょいひょいと飛び越えながら、そんな「僕」のことを詩に書いていた。彼は「人並み」に恋をし、「人並み」に結婚し、「人並み」以上の貧乏に苦しみ、ほとんど1冊の詩集を残したまま、あっけなく死んでしまった。掴みどころのない、間の抜けたような人生を送った彼の書く詩もまた、意思があるようでないような、指の間をするするとすり抜ける、かたちにならないものがある。
本稿では、このような、かたちを捉えることの難しい貘の詩を深く読むことによって、言葉にできないこの詩人の魅力は、どのようにかたちがないのか、一体、なにを捉えることができないのか、を読みとくことで、「見えないもの」のかたちをみていきたい。 貘の「かたち」をひも解く道筋として、第1章で貘の経歴を、第2章で人間のなかにおける貘の生きる位置を見たうえで、第3章では貘の内面に迫る行為として「詩」と「貘」との関係性を考察し、第4章では貘のもつ「ユーモア」と言われるものから、その批評精神を探っていく。
1922年、貘19歳のとき、美術学校に行くために東京へと上京するが、1カ月で中退した。家からの送金も途絶えたために、詩を書きながら知り合いの家を転々とするものの、1923年9月、関東大震災に遭い、一時帰郷する。沖縄に帰って初めて、父が退職後に手を出した鰹節製造業が失敗し那覇の家を売り払って、家族は八重山に移り住んでいたことを知る。親戚や知り合いに嫌煙された貘は仕方なく、那覇の公園や海辺で放浪生活を送っていたが、1925年23歳で再び上京。この年から本格的な放浪がはじまる。
25年から38年にかけて、書籍問屋、暖房屋、汲み取り屋、ダルマ船の鉄屑運搬業、鍼灸医学研究所、ニキビ・ソバカス薬の通信販売などのさまざまな職を転々としていた。そのため、夜は土管のなかや、公園や駅のベンチ、キャバレーのボイラー室等、折々の仮住まいの生活をし、初上京から16年間畳の上で眠ることはなかったという。この時期に書かれた詩が『思弁の苑』に収められることとなる。同じころ、出版社に勤める知人の紹介で、佐藤春夫に出会い、そこから草野心平、高橋新吉、金子光晴らと親交を深め、1936年、詩のための雑誌である『歴程』の同人となる。この雑誌は、草野心平ら詩人8名によって、1935年に創刊された。「エコールとしてではなく詩自体の常に新しい創造を目ざして個性の集りとしての『歴程』」と定められた詩壇の理念は、詩を党派の表明とみなさない、貘の詩作態度と共通するものであった7。
1937年、貘34歳の時、茨城県出身の安田静江と結婚し、38年には『思弁の苑』を出版するが、貧乏生活に変化はなかった。1939年には、東京府職業紹介所に就職し、この時から貘の人生において最も安定した時期となる。1944年の娘・泉の誕生とともに戦災を逃れて東京から茨城に疎開し、4時間近くかけて仕事場に通う生活を続けていた。しかし1948年には退職し、詩一本の生活に入る。そのことによって、不安定な経済状況に再び戻ることとなる。その頃、疎開先から東京都練馬区貫井町の月田家に6畳1間を2ヶ月間の約束で間借りするが、結局亡くなるまでの16年間をその場所で暮らすこととなる。
1958年、55歳の貘は、34年ぶりに沖縄へ帰郷し、2ヶ月間滞在する。しかし故郷・沖縄のあまりの変貌ぶりに、半年ほど鬱のような状態になっている8。その後も体調は悪化するが、入院費用も手術代もなく、貘を慕っていた朝日新聞調査部の土橋治重が奉仕帳もって、佐藤春夫を筆頭にさまざまな人々からカンパを集め、その費用をもとに入院する。1963年闘病の末、胃癌により永眠する。59歳であった。
前期と後期の作品は、その生活スタイルの変化から、詩にうたわれる内容の特徴にも変化がみられる。前期の作品には、野宿生活をしていたことから「僕」という存在を中心に、自身の存在への違和感や女性をうたった詩など、貘の安定しない、存在の浮遊感を伺わせる詩が多く作られている。また、前期でうたわれる貧しさには、貘ひとりの貧しさからくる、あきらめともいえる、身ひとつの気楽さのようなものが漂う。
後期の詩には、その身を「家族」という固定した場所に置く生活スタイルから、家族や、故郷・沖縄をうたったものなど、貘のいる位置が想像できるような、具体的な内容となっている。「貧乏」についても、身ひとつの貧乏の気楽さは消え、自分以外の「生」と生きる精神的な緊張感が存在する。前期の貧乏が肉体的な貧乏ならば、後期のそれは、精神的な貧乏だったともいえるが、このことは、肉体的・精神的貧しさというものではなく、貧しさからの肉体・精神への威圧ということができるだろう。肉体・精神が削られるのではなく、貘そのものは変化せずに「貧乏」に追いつめられ、肉体・精神が、居場所をなくしてしまう「貧しさ」である。
これら特色の異なる作品のなかで、本稿では『思弁の苑』を中心に、前期の作品を扱う。前期/後期と分けて読むことのできない、個々の魅力が貘の詩には存在するが、そのなかでも、わたし自身が、前期の作品に惹かれるものが多くある。それは、わたし自身の年齢が、貘が前期の詩を書いていた時期の年齢とほぼ重なっているからかもしれない。前期の作品には、推敲を重ね、磨きあげられた言葉によって、自身の存在への煮詰まることのない違和感が表現されている。同様にわたしも、自身の存在の浮遊感や、漠然とした自身の可能性へのあこがれなど、「若さ」ゆえの自分でも歯痒くなるような「捨てきれない」ものを引きずって生きている。その歯痒さ、「青さ」とも呼ばれるものが、前期の詩には濃厚に存在している。
戦後になると、人々の「沖縄」への関心や、社会の経済的発展に伴った一部の豊かな階級の人々の「貧しさ」を特別視する視点から、貘の存在も特別視されはじめ、テレビや雑誌などで度々、沖縄の文化や自身の貧乏生活について語る存在として知られていた9。しかし、その貘を見るほとんどの人々が、貘の存在を当時の「大衆」の「生」としてみるのではなく、「沖縄」や「貧乏」などのもの珍しいものでもみているかのような、エキゾチックな存在への興味として、認識していたようだ。
そのことからも、貘を語る一般的見解として、その詩が「大衆」の声であったことに視点を置いて語られるのは、貘の晩年の1950年代後半からのことであった。その新たな認識の代表的な例として、おなじく『歴程』の同人であった伊藤新吉は、1963年に出版された『現代詩手帳』において、貘が斜視の人生論を形成していると述べたうえで「斜視の人生論はそのどこかに批判的認識を付随する。それが現実感覚、庶民感覚となって作品を染め、世をすねたような、独特の人生的視野を形成する」と語っている10。このことからも分かるように、貘の詩への論考が本格的に行われたのは、貘の死後のことであった。
現在では、フォークシンガー・高田渡が貘の詩を歌った影響もあり、一部の若い人々のなかでは知名度のある存在になっている。高田渡のデビュー曲でもある「自衛隊に入ろう」などの曲からも分かるように、高田渡の諧謔めいた言葉からうまれる、社会への批評の精神は、貘の批評精神と重なるものがあり、高田渡はその重なるものに貘の魅力を感じ取っていたものと考えられる。文学の世界でも「沖縄」をうたった詩人としてのある程度の知名度はあるが、しかし「貘」そのものを論じたものは数えるほどしか残されていない。その貘を論じたものも「東京の根無し草の生き方との同時代的興味」として考察した竹内清己や11、「貧乏」「結婚」「文明」「沖縄」などのキーワードから貘の軌跡を探った仲程昌徳のように12、その「人生」に焦点をあてた研究が多く「詩」を中心に語られることは少ない。
本稿では、焦点を当てて語られることの少ない「詩」そのものの言葉を深く考察することを基本に、貘のかたちをみていく。ここまで、貘の概略を追ったが、このような位置に立った貘が具体的に人間のなかでは、どのような位置に立っていたのかを次章からみていきたい。
「尖っているもの」と、自身をまるで地球のなかの異物であるかのように表現しているところからも、自然のなかにおける自己の存在の疎外感をみることができる。1923年から38年の時期に放浪生活を送っていた貘は、親からの送金も途絶え、仕事も見つからず、土管のなかや、公園などで眠ることが多くあった。屋根の下で眠るという「一般的な」人間の営みを送れずに、人間から疎外された感覚を強く持っていた貘であったが、しかし、野外での生活も、満足に馴染むことができるものではなかったようだ。当時の貘は、さまざまな肉体労働を経験しているが、それらのどれも、長く続けることはしていなかった。どこか神経質な性質をもつ貘は、それらの仕事への嫌悪感というよりは、肉体労働の世界に、完全に馴染むことのできない貘自身に染み付いた性質のようなものが抵抗していたのかもしれない。貘は度々「人間の底辺」を生きた詩人であったと語られているが15、大正末期における「最下層」の人々の代表として、貘の存在をみることには違和感が残る。その当時の「最下層」の人々は「乞食」や「細民」と呼ばれ、頼れる知人もなく、通りすがる人々に金品を乞うたり、残飯を食べることで生きていたようであるが16、貘の言葉に、そのような貧しさが表現されていないことからも、貘の位置は決して「底辺」などではなかったように考えられる。しかし、その当時の「貧乏」は現代の「貧乏」とは比べものにならない貧しさであったことは確かである。
当時、土のうえで暮らすのは、近代化に伴って都市に流入したものの、屋根の下で眠る資本を持つことのできない、肉体労働者の人々であった。その外見は、つぎ布を当てた作業服などを着用した肉体労働者と、スーツを着用した「俸給生活者」「腰弁」などと呼ばれる人々などの、ひと目で階級がわかるような服装をしていたが、当時の貘は、もらいもののスーツやアルパカのコートを一年中着ているような、くたびれた「腰弁」のような服装をしていた。肉体労働の社会にも完全に馴染まなかった貘は、友人、知人から貰った服を着、詩の原稿用紙を肌身離さず持ち歩いていたため、そのかばんはいつも、意味ありげに膨らみをもっていた。実のところ、このような貘の風貌は、当時盛んな盛り上がりをみせていた社会主義者の風貌そのものであり、そんな彼が路上で眠っていると、警察に不審尋問をされることは避けられなかったようだ。そのため貘は、不審尋問を避けるかのように、あるいはなにか用事があるかのように、一晩中歩いていたという17。当時の貘からは、人間としての営みから疎外されながらも、誰かに見張られている緊張感や、風の音、寒さなどによる孤独感によって、土の世界にも完全に溶け込むことのできない、外的な力からの「尖らされた」存在であったことがわかる。
ここでもう一篇、自然にも人間にもなれない中間的な貘の存在を読みとることのできる、1935年頃に書かれた「夜景」をあげてみたい。
このような貘の足にぶらさがる地球は、彼にとってどのような存在なのだろうか。屋根の下で生活をする人々を人間の側、土の上で暮らす人々を自然の側とみるならば、「地球」という存在は自然の側であり、貘が自身の姿を投影している「浮浪人」の側であるとみることができる。そのことからも、自然と人間とのあいだの中間的な「尖った」存在である貘の足に「ぶらさがる」地球の行為は、貘を自然の世界へと引っ張るものであった。
自然の重力によって痛みだしたその足で、その重力を必死にこらえる貘は、人間の世界におおきな比重を置いていた。そもそも貘は野宿生活を興味本位に「体験」していたのではなく、当時の多くの人々が抵抗する術を持たなかったように、彼もまた、有無を言わせぬ大きな力によって、自然の生活の方へ押し流されていた人間であった。できることならば、一刻もはやく岸に揚がりたい……そんな感情を持ちながら、ぎしぎしときしむ地球の重力に、必死に耐えていたのではないか。
このように、中間的な「尖った」存在の貘であったが、ひとことで「尖った」といっても、その「尖り」にもさまざまな種類がある。なめらかな場所に木が一本生えているような異物的な尖りと、かたまりで存在していたものが、年月によって削られ、突出ななにかが浮かび上がるような、化石のような残された尖りと、尖りの在り方によってそのものの位置は変化してしまう。貘の場合、彼が沖縄という「異国」と見られていた土地から来たことや、土のうえでの生活を余儀なくされていたことなど、貘の意思とは反する異物的な、「尖らされた」尖りがあるが、他方、貘の意思としての意識的な尖りも存在している。ずいぶん昔からそこに存在し、ちょっとした震動や雨風にはびくともしない、むしろそれらによって一層、磨きかけられ、自身の存在を確立していくような遺跡のような尖りである。たとえば「数学」という詩からは、自らの意思としての「尖り」を明確に読みとることができる。
このことからみても「貘」というひとつの尖った存在のなかに、肉体的な「尖らされた」ものと、精神的な「尖った」尖りとの2種類の尖りを内包していたことがわかる。このような貘の詩からは、人々のなかから人間をみるのではなく、意識的に「尖った」場所から人々を眺め、また、強制的に「尖らされた」場所から自身を眺めるという、2つの視点から、自身とそれ以外の人間の「生」がうたわれている。
時代の潮流からはみ出し「尖った」存在としての貘であったが、その「尖り」を外部から乱されることなく、「貘」という位置を維持させていたことには、なにものにも動じることのない精神の「つよさ」があったのではないか。その精神がどのように守られていたのかを、つぎに考えていきたい。
大多数の人々は、衣替えのように季節に応じて生活を着替えて生きてはいない。人々にとって特定の生活は決まっており、季節など関係なくその生活を生きている。しかし、貘にとっての生活は、季節や人々に応じて着替えるものであった。寒くなれば、また違う柄を、土のうえで眠れないのならば、なにか、目的がある人間であるかのような柄を着てさ迷い歩き、友人に煙たがられれば、また、違う友人の柄へ……と、さまざまな場面で、さまざまな柄を着替えることによって、貘は生き、その行為によって、自身の精神を守り抜いていたのではないか。
たとえば、今着ている洋服の柄を見てみると、それはプリントされていたり、織り込まれていたり、いくら美しい柄であったとしても、わたしの体のなかまでは、入り込んでいない。柄を着る行為は、体を覆うことで寒さから身を防ぐためであり、すべてをさらけ出さないためのものである。「一般的」な人々が、自身を高めるために「柄」を着ているところを、貘は貧乏という「柄」を着ることによって、「貘」としての精神を守っていたのではないか。自身がどんなに惨めな存在になってまでも、精神を「守る」貘の行為には、精神を守りぬくことへのつよい執着が存在しているが、そのことは貘の「生きる」ことへの執着と重ねることができる。 ここまで、精神のなかにおける貘の「尖った」存在とそれを維持するための「柄」を着る行為についてみてきたが、次章では、このような位置に生きる貘の「生きる」ことへの執着とその「生」と「詩」との関係性をみていく。
貘の「喰う」行為の対象は、食物ではなく、親、兄弟、友人、地球などのさまざまな人間や物体が対象になっている。
貘にとって生きることと人々を「喰う」こととの比重は、お互いが引っ張りあっているかのように、比べることのできない重みがあり、彼にとって生きることとは、その、生きることと同じ重みを伴う「喰う」行為をしてまでも、執着しているものなのである。しかし貘の生きる現実は、もはや自身は「喰って」消えており、自分自身が生きることよりも、ただ「生きる」ことのみがひとり歩きしているようにみえる。そのように、自身を喰い、人々を喰ってまでも執着している「生」と貘とを繋げるものはただひとつ「詩」の存在のみであった。さまざまなものを「喰って」いた貘の「生」への執着は、「詩」への執着ということができる。
貘にとっての「喰う」行為には、なにごとにも変えがたい、詩から導かれる生きることへの執着が感じられる。さまざまな人々や自身を喰ってまでも、生きることや詩にしがみつく、そのしたたかさには、自身に対する冷酷さがある。「貘」というひとつの存在の意思を無視し、「詩」に喰いついて離れない姿を想像させるような、ある種の恐ろしい一面を貘は根本に持っているのではないか。貘には、詩と自己との繋がりへの揺らぐことのない確信があった。その確信によって貘は「喰う」行為を繰り返し、生きていたようである。
貘の「詩」には「詩」と「貘の詩」という2種類の「詩」が存在している。先にも述べたようにまず「詩」の存在に導かれるかたちで貘の「生」が維持され、その「貘」が生きることによって「貘の詩」がうまれるという関係性である。「詩」が貘の意思に関係なく導かれるものならば、「貘の詩」は、その導かれたものから派生する貘の意思のようなものであるといえる。伊藤新吉は、貘の詩について、「生活や人生をどこかへ放り出してしまいたいというような、それでいて生の低の方にへばりついているという、そういう否定と肯定との2つの姿勢が、矛盾することなく重なっている」と述べているが33、確かに貘の詩には、世の中への諦めのようなすねた姿勢がある一方で、その行為によって、なにかを深く批判しているような、頑丈な意思が存在する。このような一見、矛盾する行為が、ひとつの繋がりとして認識できることには、貘のなかの2つの詩の存在、そしてそのあいだにある「貘」の存在が絶妙なバランスを持ち、橋渡しをしていることが重要なのではないか。
では、詩のなかにおける貘の「生きる」位置とは、どのような位置にあるのか。その位置を理解するためには、先にあげた「転居」のなかの一節が重要になる。「石や歴史や時間や空間などのやうに なるべく長命したいといふのが僕なんだ」とうたうこの言葉は、貘そのものを表現しているかのような、彼らしい「生」への執着が感じられる。その執着は、「石や時間のように長生きしたい」といった単純な願望ではなく、誰も管理することのできない「時間」を、自らの存在によって管理してしまっている、「石や歴史や時間や空間」に対する、それらが内包する、時間の超越性への貘自身の共感と呼ぶことができる。 貘の娘である山之口泉は、貘と時間との関係性についてつぎのように語っている。
このように、「貘」はひとつの存在としての「貘」ではなく、繋がりとしての「貘」という独自の位置を維持していた。その位置にいる「貘」は社会とどのような繋がりを持ち、どのような思想を持っていたのか。次章では、貘の社会的な思想性について探っていきたい。
中野重治は、当時のプロレタリア文学運動において、特にきわだった現象として、「まったく無名の人が大量にあらわれてきたことと、かつて歌われなかった生活風景がかつて歌われなかったような叙事詩的な形で歌われて来たこと」と述べたうえで「人々はそこで詩に目ざめて詩にすすんできたのでなく、生活に目ざめたことによって詩にすすんできた。詩は、いわば彼らが生活に目ざめたことの直接の証だったわけである」と述べている36。ここで、1926年に書かれたプロレタリア詩のひとつともいえる詩をあげてみよう。
貘が詩を投稿していた詩壇は、先にもあげた『歴程』の他に『改造』や『詩行動』などの左翼系の雑誌であり、また、中学時代の貘は、大杉栄などの影響を受け、人間の階級を石炭に例えた、教員にたいする批判詩を発表したりしている41。それらのことからみても、社会主義的な思想を持った人びととは、少なからず近しい思想を持っていたことがわかるだろう。また、社会主義者などが、思想弾圧を受けていた時代であったことから、政治的な発言を控えていたとみることもできるが、貘の場合、そのような配慮とはまた異なった意識が感じられる。そこには、なににもならない「僕」主義に一貫した貘の生き方からくる、意識的な、書かないことへの意思が存在している。
金子光晴は、自身の詩と貘の詩とのちがいについて、つぎのように述べている。
貘の詩には、言葉にすることのできない、巧みな引力のようなものが存在する。たとえば光晴が吠える犬になり、社会の構造などを、知識や知性に訴えかけてくるならば、貘の場合、いまある現実を、なんども熟考し、厳選された言葉にすることによって、読者の感覚、感情のなかに、小石を投げ込み、ちいさな波紋をうみだす。ひとことで答えてくれるような、明確ななにかは存在しないが、なんだか、もやもやするような、ちいさな傷を読者につけたまま、貘は去ってしまう。その傷は、うかうかしていると、楽天的な「癒し」などという感情に包み込まれてしまう、かすかなものではあるが、そのかすかな傷には、後ろ髪を引っ張っぱられるような、捕らえたら離さない、執拗さが伴う。貘は、明瞭な批判詩を書いた詩人ではなかったが、しかし、彼が根底に持っていたものは、社会に対する痛烈な批評の精神であった。彼はその根底にある精神を、そのまま言葉にするのではなく、何度も屈折させることによって、読者に「考える」ことを要求していたのではないか。
先にあげた、金子光晴の言葉からもわかるように、貘が自身のイデオロギーを詩に表出させていなかったことは、度々言われていることだが、米倉巌はそのことについて、それを認めながらも、「しかし詩が本来、批評精神ないし諷刺の精神をもっているものだということは、貘自身がつよく認識していたことであった」と述べている46。では、貘の持つ批評精神とは、どのようなものだったのか。そのことを理解するにあたって、『思弁の苑』のなかでも、とりわけ貘の思想性が表出されている、「鼻のある結論」を読むことからはじめたい。
僕の鼻が「臭い」に苦しんでいる事実を「詩人がどんなに詩人でも 未だに食わねば生きられない」と、自身が汲み取り屋をして「食わねば」ならない現実と照らし合わせ、「文化」と「非文化的文明」との対立する性質に、板挟みにされた自らの位置を暗示させている。貘のいう「非文化的文明」とは、人間の文化、人間の自然発生的な意思を無視してうまれた文明、例えるならば独裁的な流れを持ちはじめた社会を示しているのではないか。そのような関心を「文明論」へと派生させ、さらにその「文明論」を「ソヴィエット・ロシヤ」や「ナチス・ドイツ」などの、社会的関心へと広げている。ここで挙げられる「ソヴィエット・ロシヤ」「ナチス・ドイツ」「戦車」「神風号」49「アンドレ・ジイド」50は、貘にとっての、「文明」の代名詞として挙げられていることがわかる。貘のいう「文明」とは、先に述べた、文化を無視して生まれた文明である「非文化的文明」を指しているようだが、例外的に「アンドレ・ジイド」のみは、「非文化的文明」ではなく、文明の本来あるべき姿として表現されていたことがわかる。「文明のどこにも人間はばたついてゐて」と表現する貘の言葉からは、自身の嗅覚である「鼻」が「非文化的文明」に翻弄されているように、人間の社会も同様に「非文化的文明」に翻弄されている姿を重ね合わせ、社会の独裁的・専制的流れを「嗅覚」という極めて個人的な視点から批評している。
このように「鼻」という、一見「文明」とはなんの関係のないようなものから「文明」の本来あるべき姿をみる貘の詩は、貘の生きる姿勢と重なるものがある。世の中が、思想性や党派でわかれ、多数派がものをいう時代において、「個」の視点から社会をみる貘の詩には、社会にたいする「感覚」としての違和感が表現されている。金子光晴は『思弁の苑』の序文のなかで「貘君によつて人は、生きることを訂正される。まづ、人間が動物であるといふ意味で人間でなければならないといふ、すばらしく寛大な原理にまでかへりつく」51と述べているが、確かに、貘の詩の頑丈さは、人間が本質的に根ざした「感情」や「感性」から発しているところにある。貘は詩のなかで、自身の思想や主張を表現するのではなく「僕」の現実をうたうことによって、その位置からしか表現することのできない「いま」を表現していたのではないか。そのような「貘」の視点からうたわれた詩には、時代の流れによって薄められることのない「貘」としての濃厚な色が現在でもみることができる。何十年も前に書かれた貘の詩が、色あせることなく、わたしのなかに響いているその理由は、その言葉が「僕」という個人から発せられていることにある。「僕」の視点から、さまざまなものをうたったその位置が、時代に消されることのない、濃厚な「いま」を維持する貘の詩のつよさとなり、現在でも詩が色あせることのないちからとなっているのではないか。
本稿では、貘の詩を読みときながら、1章では、貘の生涯の流れを追い、2章では「尖った」貘の存在とその「尖り」を守るための「柄」を着る行為をもとに、人間のなかにおける貘の位置をみた。3章では貘の内面的な「生」と「詩」との関係性を探るために、彼の内面にある、「詩」「貘」「貘の詩」という3つの関係性を考察した。また4章では、貘の思想性を探り、彼の持つ「ユーモア」と呼ばれるものの存在と、その批評精神をみた。本論のはじめにも書いたように、わたし自身が貘の詩のどこに惹かれ、どのようなところに「かたち」のなさを感じているのかをさぐる行為として、ここまで進めてきたが、いま「貘」の「かたち」として浮かびあがるのは「尖り」としての貘の位置からうまれたであろう「冷酷さ」である。どこか、世の中をばかにしたような、自身の「生」などは投げ捨てたような「冷酷さ」が、貘の根本を形成しているのではないかと、今になっておもうが、その「冷酷さ」を表現する言葉を、ここまで書いた現在も、わたしは持ち合わせることができずにいる。
「冷酷さ」を考えるなかで、わたしのなかに、ある映画のシーンが思い出された(『レネットとミラベル/4つの冒険』)52。それは、主人公の少女が、夜と朝のあいだの「青い時間」をみるために、朝とも夜とも言えない時間に起き出して庭に立つ場面だった。庭に立って外の音を聞くただ、それだけの場面であるが、その「青い時間」には、朝の鳥は目ざめず、夜の鳥は眠りについた、だれもが眠った「沈黙」の瞬間があるのだという。たしかにその瞬間は、なにも「ない」瞬間だった。その「ない」場所には、「夜」や「朝」といった余計な観念が排除された、ただその「ない」瞬間のみの、広さのようなものが存在していた。主人公のレネットは、その「青い時間」をつぎのように表現している。
世の中には、自分の意思でそうなったのではなく「こうなるしかなかった」という追いつめられた状況のもとでうまれる、さまざまな「かたち」にならないものがあるようにおもう。その、かたちにならないものにこそ、わたしたちがみるべき「かたち」があるのではないか。「見えないものをみる」とは、そのような行為をいうのではないか。
わたしは「かたち」にならなかったもの、視覚に映らなかったものを、みることのできる目を持っていたい。「みえる」のを待つのではなく、「みる」行為を意識的に行っていかなければならないのだとおもう。
・山之口貘『思弁の苑』むらさき出版部、1938
・山之口貘『山之口貘全集』全4巻、思潮社、1975-1976
・山之口貘『山之口貘詩集』(現代詩文庫1029)思潮社、1988
・山之口貘『永遠の詩③山之口貘』小学館、2010
*
・伊藤信吉『現代詩鑑賞講座』第8巻、角川書店、1969
・茨木のり子『うたの心に生きた人々―与謝野晶子、高村光太郎、山之口貘、金子光晴』さえら書房、1967
・井伏鱒二『山椒魚』新潮社、1998
・荻原昌好『少年少女のための日本名詩選集』9、あすなろ書房、1986
・加藤典洋『日本という身体「大・新・高」の精神史』講談社、1994
・金子光晴『金子光晴全集』第13・14巻、中央公論社、1976-1977
・金子光晴『金子光晴詩集』岩波書店、1991
・佐藤春夫「放浪三昧」『定本 佐藤春夫全集』第10巻、臨川書店、1999
・笹沢美明、他『日本詩人全集』33、昭和詩集(1)、新潮社、1969
・高良勉『僕は文明をかなしんだ』彌生書房、1997
・武田弘『戦前の日本』彩図社、2009
・中野重治『日本現代詩大系』第8巻、昭和期(1)、河出書房、1951
・仲程昌徳『山之口貘・貘とその軌跡』法政大学出版局、1975
・山之口泉『父・山之口貘』思潮社、1985
・山之口泉・沖縄タイムス社『アルバム・山之口貘』沖縄タイムス社、2003
・米倉巌『金子光晴・戦中戦後』和泉書院、1977
・竹内清己「山之口貘-地球の詩人-」『国文学 解釈と鑑賞』59巻5号、至文堂、1984
・米倉巌「山之口貘の位置」『昭和詩人論』有精堂出版、1994
・高田渡、大工哲弘ほか……『山之口貘をうたう』B/Cレコード、1998
・Eric Rohmer 『レネットとミラベル/4つの冒険』シネセゾン、1986
京都の大学を卒業後、京都と長野を往復しては、自らの人生を模索中。







